
結婚式の費用について「総額350万円」といった数字を耳にすると、負担の重さに不安を感じる方もいるでしょう。しかし実際には、ご祝儀や親族からの援助により、新郎新婦が準備すべき金額は総額よりずっと少なくなります。
とはいえ、状況によってはご祝儀だけでは費用を賄えないケースも存在します。本記事では、結婚式の自己負担額の実態と、準備すべき金額の目安について解説します。
結婚式費用の総額と自己負担額の計算方法
結婚式における自己負担額とは、式全体にかかる費用から「ご祝儀」と「親族からの援助」を差し引いた金額を指します。計算式は以下の通りです。
自己負担額 = 結婚式の総額 - ご祝儀 - 親族からの援助
三菱UFJ銀行のコラムによると、全国の結婚式費用の平均総額は327万円から374万円程度となっています。一方でご祝儀の総額平均は約200万円から230万円、親族からの援助は約160万円から190万円が目安です。
つまり、これらを差し引いた自己負担額の相場は100万円から160万円程度となります。総額の半分以下、あるいは3分の1程度で済むケースが多いのです。
ご祝儀の相場と実際に集まる金額
自己負担額を左右する大きな要素がご祝儀です。招待客一人あたりの平均は約3万円とされていますが、実際には関係性によって金額に幅があります。
| 招待客の続柄 | ご祝儀の相場 |
|---|---|
| 友人・同僚 | 3万円 |
| 上司 | 4万円~5万円 |
| 親族 | 7万円~8万円 |
招待客が50人の場合、単純計算で150万円のご祝儀が見込めます。ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は招待客の構成によって変動します。
親族の割合が多ければご祝儀総額は増えやすく、友人中心であれば一人あたり3万円前後と想定するのが現実的です。計画を立てる際には、やや控えめに見積もっておくと安心でしょう。
ご祝儀では賄えないケースとその理由
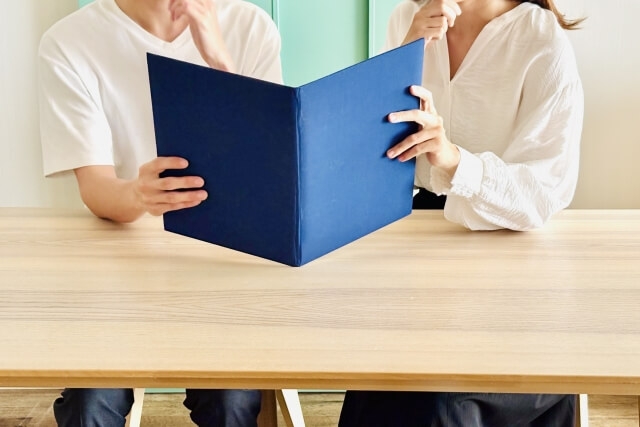
ご祝儀があっても自己負担額が想定以上に膨らむケースがあります。主な理由は以下の通りです。
招待客の人数が少ない場合
少人数の結婚式では、会場費や衣装代といった固定費の割合が高くなります。招待客30人以下の式では、ご祝儀総額が90万円程度にとどまる一方、式場によっては総額が200万円を超えることもあります。
結果として自己負担額が100万円以上になるケースも珍しくありません。人数を減らせば費用も減ると考えがちですが、実際には固定費の影響で自己負担額が増えることもあるのです。
式場のグレードや演出にこだわる場合
有名ホテルや人気のゲストハウスを選ぶと、一人あたりの単価が高くなります。料理やドレス、装花、映像演出などにこだわりを持つほど、総額は膨らんでいきます。
ご祝儀一人あたり3万円に対し、実際のゲスト単価が5万円を超えるような会場では、その差額分が自己負担として上乗せされます。見積もり段階で単価を確認し、予算内に収まるか検討することが重要です。
親族からの援助が見込めない場合
約8割のカップルが親族から援助を受けているというデータがありますが、全ての家庭で援助があるわけではありません。経済的な事情や方針により、援助を辞退するカップルも存在します。
親族からの援助がない場合、ご祝儀だけでは総額の6割程度しか賄えません。残りの4割、つまり150万円前後を自分たちで用意する必要が出てきます。
自己負担額を抑えるための工夫
自己負担額を減らすには、費用の見直しと計画的な準備が欠かせません。具体的な方法をいくつか紹介します。
- オフシーズンや平日の割引プランを活用する - 春秋の人気シーズンを避けることで、会場費が2割から3割安くなることがあります。
- 持ち込み可能な項目を増やす - 引き出物やペーパーアイテムを外部で用意すれば、式場価格より安く抑えられます。
- 優先順位を明確にする - 料理や衣装など譲れない部分にお金をかけ、装花や演出は予算内で調整するといったメリハリをつけます。
- 複数の式場で見積もりを比較する - 同じ内容でも式場によって価格差が大きいため、3カ所以上の見積もりを取ることをお勧めします。
また、ブライダルフェアに参加すると、成約特典として数十万円の割引が受けられることもあります。こうした機会を上手く活用することで、自己負担額をさらに減らすことが可能です。
自己負担ゼロで結婚式を挙げられるケース
実は、自己負担額がゼロ、あるいはマイナス(黒字)となるカップルも存在します。約8%のカップルが、ご祝儀と親族からの援助により、手出しなしで結婚式を実現しているというデータもあります。
自己負担ゼロを実現する条件として、以下が挙げられます。
- 招待客が60人以上で、ご祝儀総額が180万円を超える
- 親族からの援助が200万円近く見込める
- 格安プランや特典を最大限活用し、総額を350万円以下に抑える
ただし、これらの条件が揃うケースは限られます。自己負担ゼロを目指すあまり、本来やりたかった演出を諦めるのは本末転倒です。あくまで目安として捉え、無理のない予算計画を立てましょう。
支払いのタイミングと資金準備の注意点
結婚式の費用は、多くの式場で前払い制が採用されています。式の1週間前から1カ月前までに全額を支払うケースが一般的です。
つまり、ご祝儀を受け取る前に総額を用意しなければなりません。親族からの援助がある場合も、支払い期日に間に合うよう事前に話し合っておく必要があります。
一部の式場では当日払いや後払いに対応していますが、選択肢は限られます。式場選びの段階で支払いスケジュールを確認し、資金計画を立てることが大切です。
どうしても資金が足りない場合は、ブライダルローンという選択肢もあります。低金利で借りられる商品も多いため、計画的に利用すれば無理なく返済できるでしょう。
予算計画を立てて理想の結婚式を実現しよう
結婚式の自己負担額は、総額からご祝儀と親族からの援助を引いた金額であり、相場は100万円から160万円程度です。ただし、招待客の人数や式場のグレード、親族からの援助の有無により、この金額は大きく変動します。
ご祝儀だけでは賄えないケースとして、少人数の式や高級会場を選んだ場合、親族からの援助がない場合などが挙げられます。自己負担額を抑えるには、優先順位を明確にし、割引プランや特典を活用することが重要です。
まずは招待したい人数と式場のイメージを固め、複数の見積もりを取って比較しましょう。支払いのタイミングも考慮しながら、無理のない予算計画を立てることで、理想の結婚式を実現できるはずです。